横山 浩二(救急救命士)
救急救命士取得後、一般企業に入社。医療機関以外でも働くことができる医療職のプラットフォームを作るために活動中。現在、医療従事者だけで運用している医療メディアの運営。

こんにちは、hospass運営局です!医療系情報メディア【hospass】では病院はパスする時代というスローガンを掲げ、日常お役立ち情報や病院の外でも活躍している医療職の取材記事を発信しております!どうぞご覧ください!

今回は救急救命士の資格を持ちつつ、現在医療機器メーカーの事業部長として活躍されている横山さんを取材させて頂きました!
横山さんが救急救命士になった理由は?

高校生の時はずっとスポーツバカだったんですよ(笑)
高校3年生になって受験が近づいて来ているのに、年末までずっとサッカーをしていて「どうしよう。行きたいところ全然決まってない。」と少し焦っていました。
そんな中、獣医であった叔母に相談したら、「浩二は人のために仕事したほうがいいと思うよ。救命士っている資格があって、パンフレットもあるから一回オープンキャンパス行ってきなよ。」とアドバイスをもらったんですよね。
そして実際にオープンキャンパスに行って、心肺蘇生法や気管挿管、薬剤投与など、レスキューの模擬実習を見て、「めっちゃかっこいいな!」と思って救急救命士になりました。
大学3年生での転機と恩師との出会い

大学3年生まで本当にチャランポランでした(笑)
毎日飲みに行くことや、遊んでばっかりのとある日に、教授の推薦でOBを紹介してもらいました。
その方が僕の恩師にもあたる鈴木健介さんなんですが、救急救命士の資格が取得できる日本体育大学保健医療学部の准教授をしている方です。
勉強を全くしておらず、遊んでばかりだった僕にかけてくれた一言が本当に心に刺さったんですよね。
お前はバカか。なんのためにこの学科に入ったのか忘れたのか?お前は本当にそれでいいのか?

この言葉が、僕を大きく変えましたね。
健介さんから、学生の時に学生団体を立てたり、イベントを企画運営を行ったりした話を聞き、「時自分も何か学生時代に打ち込むものがないとやばいな。」って思ったんです。
そこから一気にエンジンをかけて、救急救命士の学生団体を立ち上げました。
10人に聞いて10人にやるなと言われた学生団体

学生団体の立ち上げにはみんなから反対されましたね(笑)
医療系団体に参加している他のOBや先輩に「学生団体を立ち上げてみようと思うんですけど、どうですか?」と聞いたら、全員に「やめろ」と言われました(笑)
「勉強もしてなくて成績が悪いお前が、学生団体を立ち上げたからってどうなるんだ?」と、もうバッシングでしたね。
とにかく自分としては、何かに打ち込むものが欲しいと思っていたので、勉強よりも団体の立ち上げがしたいと思って、最初は1人で活動してました(笑)

団体としての最初の活動内容は、救急救命士を普及するために、心肺蘇生法や挿管、薬剤投与など、メディカルラリーみたいな、楽しく誰でも参加できるようなイベントを施設を借りてやっていたんです。
1人で活動を続けていたんですが、当時大学で一緒にいたメンバーの2人も協力してくれるようになって、徐々に活動が大きくなっていったことを覚えています。
当時はmixiが主流で、「救命士学生団体をやってるんです」というDMを送ったりして、他の救急救命士養成学校に連絡したりしていました。
帝京大学、帝京平成大学、杏林大学という3つの大きい大学も活動にジョイントしてくれて、3か月くらいでメインのメンバーが30人くらいになり、イベントと勉強会を年間24回くらい開催してました。
就職の時に気づいた、自分が本当にやりたいこと

大学3年生から学生団体を立ち上げて、親も学校の教授も「東京消防庁に行って君は華々しく現場にでるんだな。」と言ってました。
公務員資格を取るために大原専門学校に通っていましたが、親に内緒ですぐにやめたんです(笑)親父にすぐにバレて、ものすごく怒られました。
公務員になったら、「ああしてみたい!」「こういうこと変えてみたい!」と思った時、実行するまで時間がかかる。もっと自由に自分の発想やアイデアを形にしたい!一般企業に入って、救急救命士を認めらえるようにしたい!
と、親にプレゼンをしたことを覚えています。その後、一般企業の就職活動を始めて、ALSOK(アルソック)に入社しました。
資格を取ってから、現場に一切行かなかった異色の経歴
アルソックに入った理由は、救命士の資格を活かして民間の救急隊を作りたかったからです。
新卒で入社して、意見箱に企画を書きまくりました。意見箱って、名目が”どの社員でも意見を載せていい”というもので。それならと思って、ずっと意見を載せていたら役員の人から連絡が来て「そろそろやめてもらえますか」と言われました。

それでもしつこく意見を載せていたら、役員の人に「もう意見は良いから、1回来てくれ」と言われて直接プレゼンをしました。
役員にプレゼン後、いまだにアルソックに受け継がける企画が誕生
役員の方に、自分がやりたい企画を熱くプレゼンしました。けれど、金銭面は全然プレゼンすることができず、結局「アルソックではできません」と言われました。
ただ、唯一通った企画が、現場に行く警備員が(医療現場のような)ゴム手袋をつけて対応することが認められて、今でもアルソックでもゴム手袋をつけてると思います。
自分自身が本当にやりたかった企画が認められなかったから、このまま警備員をやっていても仕方ないなと思って3年半でアルソックを辞めました。
このままじゃダメだと思った社会人3年目
ビジネスとしての対人のコミュニケーション能力やプレゼン能力をつけたいと思い、1番苦しい就職先を調べたら訪問営業が出てきたので、訪問営業の世界に入りました。
ほぼフルコミッションの建築営業を1年半やって、営業マン400人の中で、1年で14位までいきました。
会社にも貢献できたし、次は自分の救急救命士と言う資格をいかした仕事をしようと思って、今の会社のセキムラの社長と出会って、就職を決めました。将来の救急救命士のための雇用拡大と救急救命士が一般企業で働けるということを証明することによって、社会の救命率をあげたくて、一般企業に入り続けています。
60年目の医療メーカーである今の会社から発信していきたいことは?
将来的には、今の販売事業部を社内ベンチャーみたいな形で一つの子会社みたいな形でやりたいと社長に伝えています。決済権がうまれてくれば、救急救命士だけじゃなく、学生も含めて思いを描けれるような会社ができるかなと思っています。
学生を派遣したり、インターンを受け入れ就職までの仕組みを作ることで、就職支援とかもできるかなと思っています。また、クリニックや介護施設等、救急救命士がまだまだ活躍できてない領域に、救急救命士を派遣できたらいいなと思っています。
僕は、一般に救急救命士を広める仕組みを作りたい、助けられる人を増やしたいという思いから、一般企業に入っています。自分がこうやって一般企業で働けば、学生も「横山さんって一般企業でめちゃめちゃいけてるなあ」っていうのもわかってくれてると学生にとっても一つの選択肢になるかなと思って、今頑張ってるっていう感じですね。
大きな野望
今後は、総合院みたいな形でいろんなメディカルに強い人たちが集まって、病院を選ぶミスマッチを減らしたいと思っています。例えば、「お腹が痛い」「頭痛がする」ということで簡単に救急車を呼ぶことも、このプラットフォームで対応することで、無駄な救急車を呼ぶ手間がなくなると思います。もっと拡大していくと、メンタル、精神領域や人の健康を支えるプラットフォームができればいいなと思っています。基本的に健康の悩みや病気の悩みが解消できれば無駄な医療費や無駄な人件費が減ってくるというのが現状かなと思いますね。
医療業界は、固い人と固くない人の差が激しいと思っています。突拍子もないことを言うと、「お前は変なんだ」とか言われることもあったり。
大事なことは「自分が何がしたいか」だと思っています。自分がどういうこと描いていて、どういうことを将来やりたくてどういうことができて、何に繋がるかということが重要だと思っていて。
それで助けられる人、貢献できる人、知識を得ることで医療業界に興味がわく人、気づきを与えられれば与えられるほど、もっとより良い医療業界になるかなと思っています。
救急救命士って、病院に入ったら看護助手からスタートするんです。多くの医療機関が救急救命士の雇用を求めるのは、看護師より安い賃金で働いてもらって、かつ「医療現場で働ける!」みたいな意識が高い子が集まるからです。でも、そこに入った救命士って「なんか違う」となって、辞めていく理由になるんです。
消防に入った子たちも、日々助けてる方々が8~9割が誤報なんです。1割だけが、コードブルーにあるような高エネルギー外傷とか緊急性の高い心筋梗塞とかです。

熱い想いで救急救命士が消防に入ったにも関わらず、そんな毎日になると疲弊していってしまいます。
だからこそ、自由にやれること、自分のやりたいことやアイディアが吸い上げれるようなところがどんどん増えていったらいいなと。
メディカルの知識が必要じゃない現場は、その専門性がある人たちはわざわざ行く必要はないと思っています。アメリカみたいに、パラメディックは重症な時しか行かなくて、ほかは民間の会社一般企業が救急車を出して対応するというのが、本当に理想的だなと思います。そうでないと、無料だから呼んでしまうことが続いてしまいます。
いろんな働き方、アイディアが形にできるところがあるのに、知っているか知らないかで全然違うと思います。そういう道しるべを、形にできるようにしていきたいと思っています。
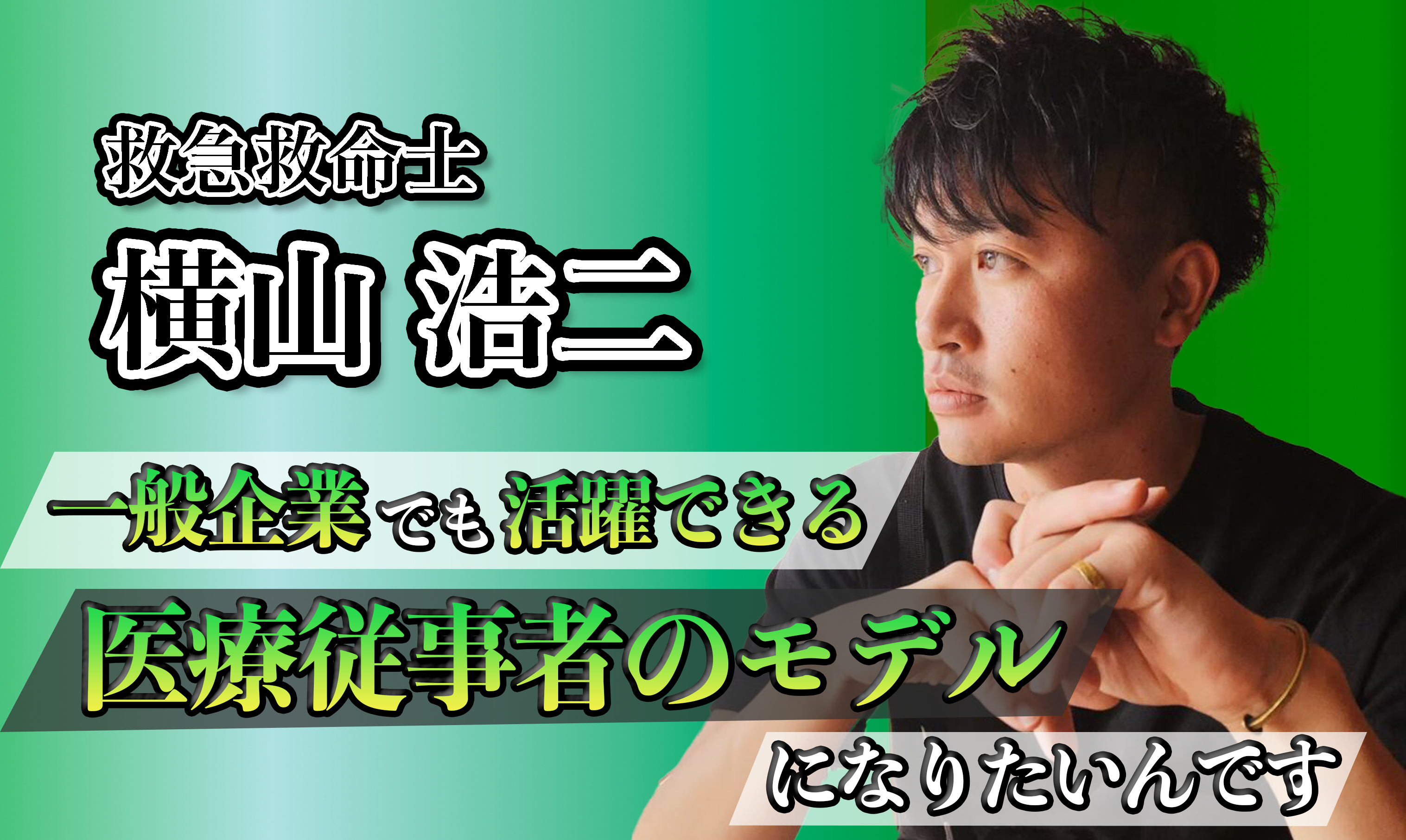
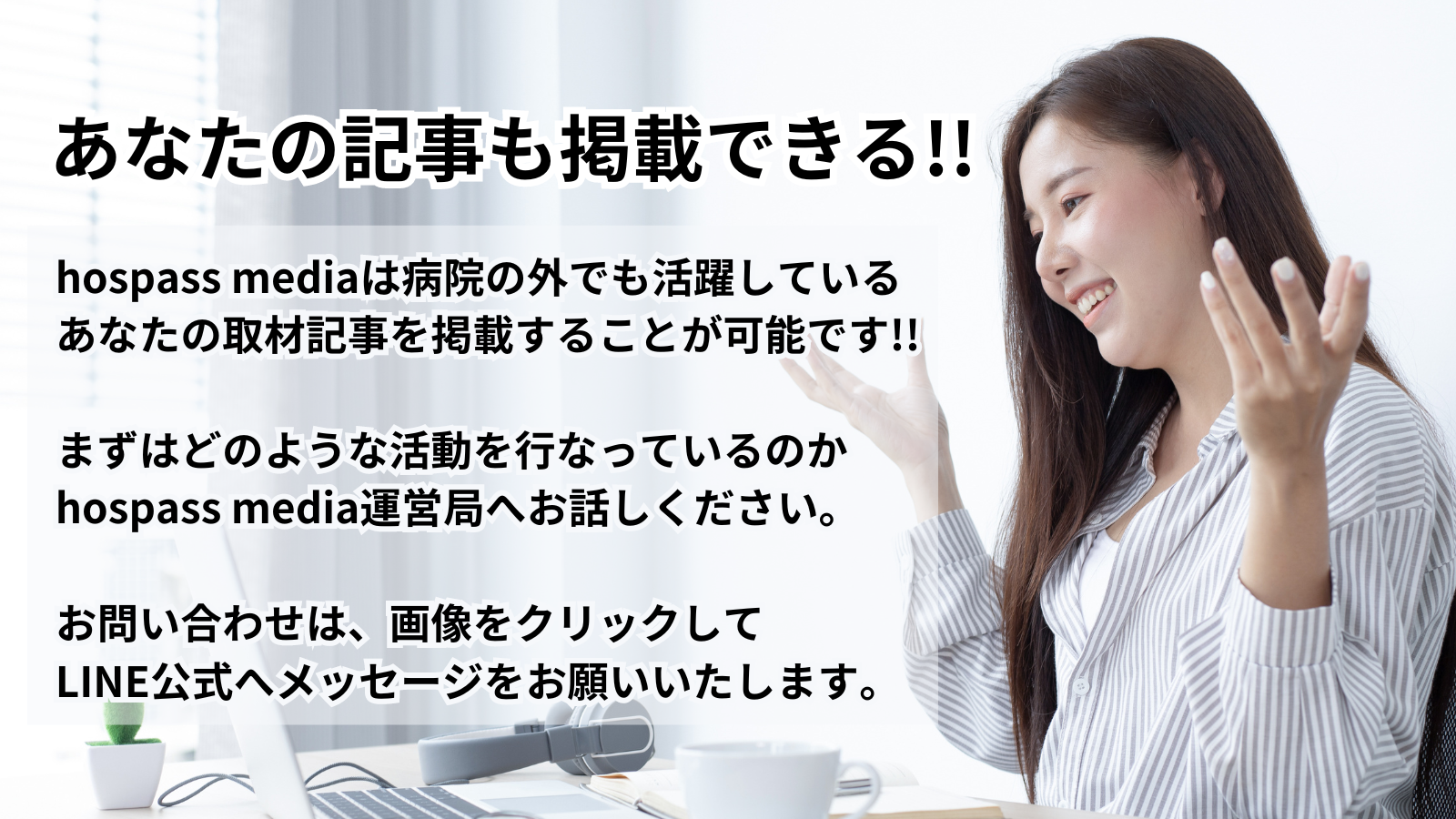

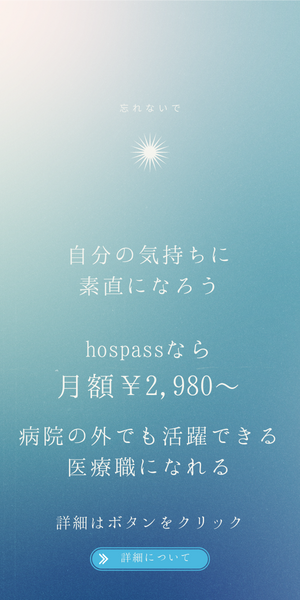

コメントを残す