取材日:2023/07/24

こんにちは、hospass運営局です。“病院はパスする時代”を創造するべく、医療職限定でチームを組み活動を進めています。
社会福祉士の資格を持ちつつ、現在はメンタルサポーターとして活動されていた塩田剛士さんを取材させて頂きました!
- 祖父の闘病経験がきっかけで医療福祉の道へ
- 病院での経験を経て、より広い範囲でのサポートを目指すことに
- 人生の転機となったコーチング体験
- がん患者さんや心に悩みを抱える人々への寄り添いを目指す
祖父の闘病が導いた福祉への道

「おじいちゃん、寂しくないのかな」という思いが原点でした。
中学3年生の頃に、祖父が末期の肺がんと診断されました。大学病院に入院して治療を受けたのですが、診断の時点で末期だったので亡くなるまでの約半年は入院生活でした。
面会時間が終わると「お帰りください」と言われて、祖父の状況に関わらず家族も帰らなければならない。
祖父が亡くなってから間もない時期に、母親から山崎章郎先生の『病院で死ぬこと』という本を勧められ、初めてホスピスの存在を知り将来は「ホスピスで働きたい」と強く思いました。
今の時代なら臨床心理士や公認心理士を目指したと思うんですが、当時の心理職は大学院まで行かなきゃいけない割にはステータスもお給料も高くなかったです。かといって医者になるほど頭も良くないし、看護師になるほど理系も得意じゃなかったため福祉の道に進みました。
病院での経験を通じて感じたことは?

就職した当初は医療ソーシャルワーカーの認知度が低かったので、やりたい仕事ができるまでに時間がかかりました。
本当は、実習先だったホスピスのある病院に医療ソーシャルワーカー(以下、MSW)として就職したかったんです。
でも当時はMSWの認知度が低くて叶いませんでした。一部では「MSWの業務である『相談』は看護師がやればいい」という声があったみたいです。
大学卒業ギリギリでなんとか決まった就職先は、実家から通える療養型の病院でした。
最初は介護職として入職。それから2〜3年して相談室の欠員が出たことをきっかけに、事務職を経て正式にMSWとして採用されました。
念願の病院で働けたのは28歳のときです。「ホスピス病棟の看護助手として働かないか」と誘われて、看護助手での採用でしたが、迷わず承諾しました。
ところが、数年ほど経ってから病院の医療機能評価があって、患者さんの心のケアや精神的な支えになる人が必要となり、相談業務も兼務できることになったんです。
僕としては願ったり叶ったりで、本当に嬉しかったです。

憧れの場所でMSWとして働く中で、新たな課題にも気づきました。
病院では、主にその病院に入院している患者さんやご家族からの相談を受けていました。でも、地域の中で仕事や日常生活を送りながら闘病している患者さんたちのニーズにも応えたいと思うようになったんです。
また、病院でのがん治療が終わった後の患者さんの行き場の問題も気になりました。
介護施設に入れなかったり、がん患者さんの在宅介護が難しかったりして、ホスピスを選択するケースにも遭遇しましたね。
さまざまな事例を知るうちに、自分で “ 患者さんが転々としなくても最後までいられる場所 ” を作れたらいいなという思いが膨らんで、サービス付き高齢者住宅でも働きました。

その後もいろいろな職場を経験しましたが「ホスピスに携わりたい」という気持ちはブレずにありました。
ただ転職を重ねるごとに、気づけば理想とする環境から遠ざかっていたんです。合わない環境で働いたことで、適応障害になったこともありました。
今の活動をはじめたきっかけを教えてください

コーチングを受けて「ホスピスでの相談業務にこだわらなくてもいい」と思えたことが、大きなきっかけでした。
2020年に2つのコーチングを受けました。
1つ目は、看護師の知人が受講していた組織マネジメントのためのコーチングスクールです。体調を崩していた時期だったので「きっと良い方向に変わると思うよ」と、おすすめしてくれました。
2つ目は、SNSで知り合った元MSWのメンタルコーチからコーチングを受けました。最初は経済的な理由で躊躇しましたが「塩田さんは変わりたいと言ってるのに、それでいいんですか?」と言われて、コーチングを受けることを決意しました。
コーチングを受けたことで視野が広がり「ホスピスでの相談業務にこだわらなくてもいいんじゃないか?」と気づいたんです。
この気づきが今の活動につながっていると思います。
なぜホースセラピーをはじめたのですか?

ホースジャーナリストさんと出会って「それならできるかも!」と思ったからです。
ホースセラピーでは、馬とのふれあいを通して心身の癒し効果が見込めるとされています。
僕自身も定期的に乗馬クラブに通っていた時期があるのですが、馬とふれあうことによってストレスへの耐性が上がると感じていました。
しばらく乗馬クラブに行けないときは「良いこころの状態を保てない」と思ったほどです。
以前からホースセラピーに興味があったのですが、馬を購入するお金もなければ、馬のお世話をする技術もないので、ずっと「やりたいけど無理だろうな」と思っていました。
転機となったのは、SNSでの出会いです。
SNSでホースジャーナリストの方と知り合って「土木作業や馬の世話は馬のプロに任せて、塩田さんは人との関わりという専門性を活かせばいいと思いますよ」というアドバイスをもらったんです。
そのアドバイスを聞いて「全部を自分でやらなくてもいいんだ」と、すごく肩の力が抜けました。
2024年3月には個人事業主として開業して、ホースセラピーをはじめとした事業を本格的に進めています。がん患者さんとご家族向けの「がん患者さんとご家族のお話の場 あゆみ」、「ほめ日記講座」なども行っています。
塩田さんの活動の原動力を教えてください!

「がん患者さんとご家族に寄り添って、心のケアをしたい」という気持ちです。
さまざまな職場を経験し、今は個人事業主になりましたが「がん患者さんとそのご家族に寄り添って、心のケアをしたい」という気持ちは、ずっとブレていません。
これまで関わってきたホスピスやホースセラピーでの仕事は、私のアイデンティティのようなもの。もし違う仕事に就くことになったら「自分の存在価値って何だったんだろう」と感じてしまいそうなんです。
それと、現実的な事情もひとつの原動力です。
「がん患者さんとそのご家族に寄り添って、心のケアをしたい」という想いや、やりたいことを貫きたい気持ちがある一方で、収入も得ていかないといけない。
バランスよく考えたり行動したりすることが下手なので、周りにサポートしてもらいながら、慎重に確実にできることから進めています。来年50歳を迎える節目ということもあり、40代最後の1年間で思い切り挑戦したい気持ちもありますね。
事業を通して伝えたいことを教えてください!

つらさをギリギリまで背負い込んだり我慢したりしなくてもいいんです。
がんの方や心の病を抱えている方など、自分のつらさを一人で抱えている方がとても多いと思うんです。
僕は、そういう方々が「ギリギリになるまで背負い込んだり我慢したりしなくてもいい」と思えるような存在でありたいと思っています。
それと、僕が取り組んでいるホースセラピーや相談の活動は、まだ広く知られていない部分があるかもしれません。医療従事者でも「聞いたことはあるけど、具体的に何をする人なの?」「ホースセラピーって何?」と思っている方が多いと思います。
僕が「メンタルサポーター」という肩書きで行っている活動内容や、そこに馬が関わることでどのような良い効果があるのかも、より多くの方に知っていただきたいです。

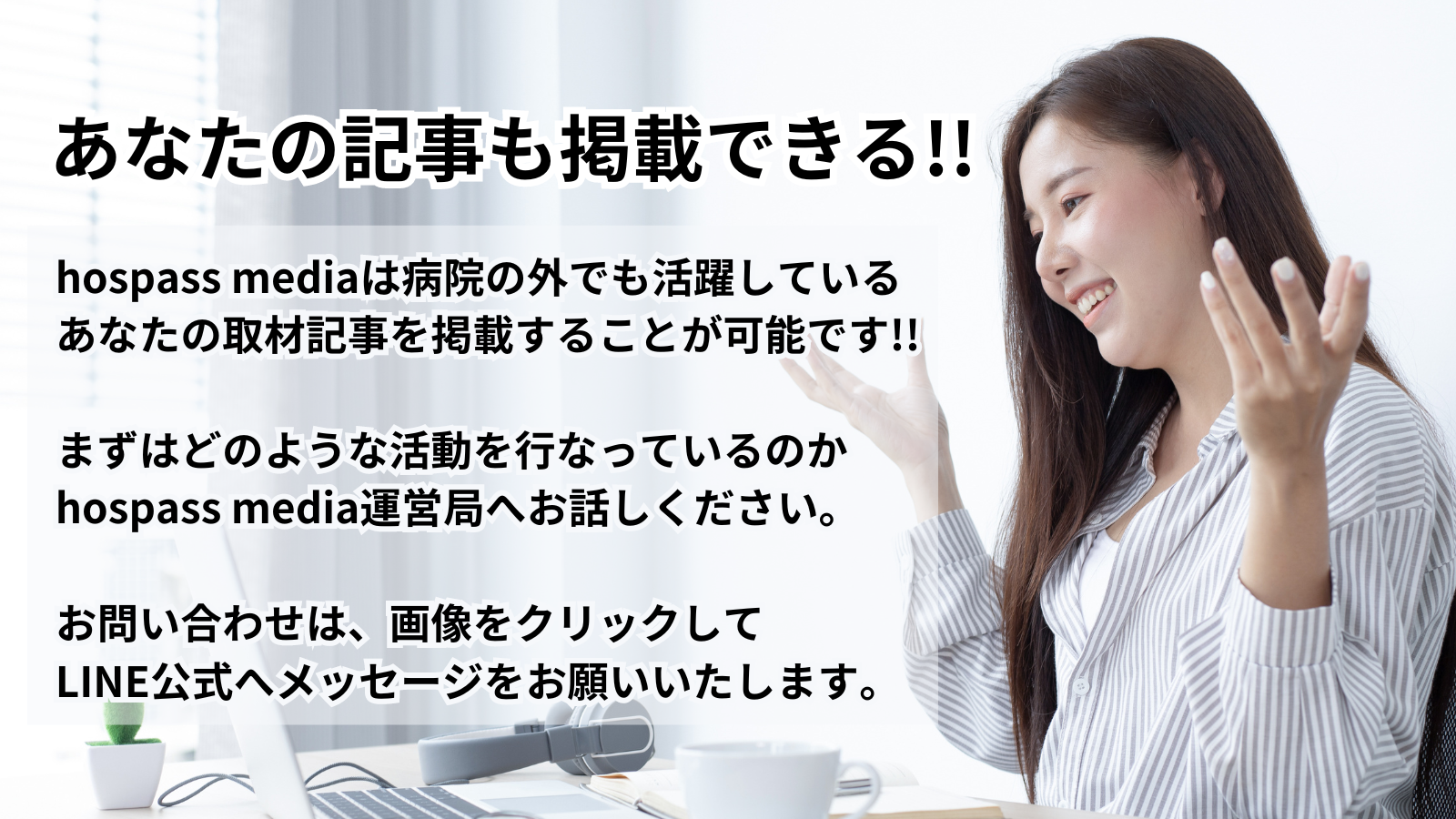

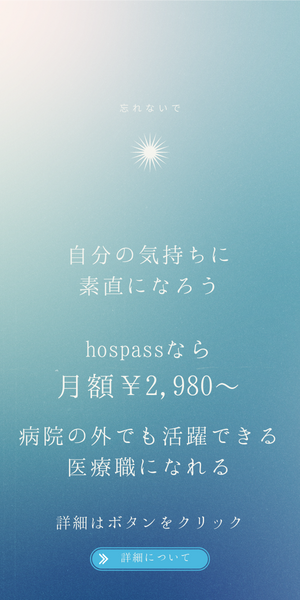

塩田剛士(社会福祉士)
医療ソーシャルワーカー経験を活かして、現在はメンタルサポーターとして活動中。馬とのふれあいを通じた「ホースセラピー」や、がん患者さんとご家族向けの個別セッションなど、新しい形の心のケアを提供している。