※当メディアのポリシーに基づき「患者さま」に表記を統一をしております。
- 同級生を失って気づいた医療とお金の関係性
- 看護師が輝ける社会を創りたい
- 医療者は医療業界以外でも求められている!
医療従事者になろうと思ったきっかけを教えてください

医療経済に興味があったからです
小学2年生の時に、同級生が交通事故で命を落としてしまう経験をしました。とても衝撃的な出来事で、すごく悲しかったことを覚えています。そのときに同級生の角膜は誰かに移植されて、今も生き続けていることも知りました。
亡くなった命が誰かの命につながっていくことに驚きを感じ、医療に興味を持つようになりました。
中学3年生のときに、授業で出された課題に取り組むため、自分で問い合わせてアイバンクの見学に行きました。そこで、角膜移植は寄付金で成り立っていることを知ったんです。
角膜移植によって幸せになる方がいるのに、どうしてビジネスが成り立っていないのか。相手に喜んでいただくことで、収入を得られると考えていたので、疑問に思いました。医療業界では相手に喜んでもらうことをしてもお金がもらえないケースがあることに違和感を感じ、医療経済に興味を持ち始めました。
看護師を選んだのは、患者さまの声を一番聞ける職種だと思ったからです。
また、医療の仕組みは医療政策によって決まるため、現状を変えるには政治への働きかけが必要だと感じました。政策を変えていくためには数が必要だと思っていたので、母数が多い看護師を選んだ背景もあります。
これまでのキャリアについて教えてください

さまざまな取り組みをしてきましたが、どれも熱い想いで挑戦してきました
「医療界を変えていくには教育からだ」と強く感じ、まずは教員として働きました。同じような想いを持っている医療職を増やしていきたいという想いが根底にありましたね。
しかし、看護師の仲間をパワハラで失ってしまう経験があり「根本的な解決には教育が必要かもしれないけど、今は対処療法が必要だ」と思うようになったんです。
対処療法として医療組織の改善をしていくには、大前提としてお金の流れを理解しなければならないと気づいて、医療をビジネスの観点から見た際に参考事例が多いアメリカで、医療×ビジネスについて学びたい気持ちが芽生えました。そこからは英語もよくわからないのにⅯBA(Master of Business Administration)を取得するべく渡米して、大学院で勉強する生活が始まりました。
私がMBA取得に励む中、世の中ではリーマンショックが起きていて、豚インフルエンザも流行し、たくさんの病院でストライキが起きていましたが、組織変革に注力した病院は生き残り続けたことを知りました。生き残った病院にはコーチング職がいたそうです。
医療の組織変革にはコーチングが必要だと確認し、MBAを取得してからは上場しているコーチング企業である「コーチ・エィ」に就職しました。看護師が輝ける舞台をつくりたいと考えていた私にとって、コーチ・エィが医療業界に挑戦しようとしていたことが就職の決め手でしたね。
コーチ・エィを辞めて独立してからは、無医地区での診療所や訪問看護ステーションの開業、医療AI会社の起業をしていました。事業の立ち上げだけでなく、本の出版やドラマの監修なども経験しました。
活動に詰まっている想いを教えてください

みんなを笑顔にしたいです!
講演依頼をいただいた際には「医療従事者の笑顔が患者の笑顔をつくる、患者の笑顔が家族の笑顔をつくる、家族の笑顔が地域の笑顔をつくる」という言葉を必ずお伝えするようにしています。医療従事者が輝いて活躍できる舞台をつくれるように精進していきたいと、常に思っていますね。新しいことを常に開拓していくことが好きなんです。
同時進行で複数の事業を展開していますが、根本には「みんなと同じことをするよりも逆を向いて行動したい」という気持ちがあります。自分で言うのもなんですが、あまのじゃくなんです(笑)。
今後も新しいことの開拓を常にしていきたいですね。私は人の可能性を広げるのが好きですし、自分が道を切り拓けばあとは仲間がやってくれると思っています。
体調を崩し、会社を事業承継した経験もしました。今はさまざまな企業と連携して活動して、ビジョンに向かって歩んでいます。
今後の展望について教えてください

医療業界にもⅮXは必要です
今後は、医療ⅮXに携わっていきたいです。経済産業省がⅮXの推進を2020年に発表した後、医療業界でⅮXの話が出てきたのは2022年のことでした。
少子高齢化によって人口減少していくことが確定している日本で、患者さまの全体数は増えていくけれど、医療従事者の全体数を増やすことは難しいですよね。世の中全般と同じように医療従事者も「数を増やす段階」から「働き方の質を上げる段階」に変わってきていると思います。
最近でこそ耳にする機会が増えたDXという言葉は、ICT化やデジタル化とは異なり、業務再構築という意味が含まれています。
新しい概念で試行錯誤しているところが多いので、現在、いろいろな病院や都道府県看護協会・連盟から看護DXに関する講演や研修依頼をいただいています。
全米ナンバーワンと言われることの多いメイヨークリニックでは、いち早く患者さまへの治療説明にYouTubeを取り入れていましたし、医療業界におけるⅮXの推進は今後のキーになりそうですね。
医療従事者は可能性の塊です。医療業界の中で活躍することも、もちろん大切なことです。しかし、みなさんが思っている以上に医療業界以外にも私たちのような人材を求めてる人がたくさんいることを知ってほしいですね。
医療従事者に向けてメッセージをお願いします

資格があるからこそチャレンジしよう!
医療従事者に対しては、国家資格があることを安心材料にして、いろんな挑戦をしてほしいと強く思います。まさに「病院をパスする」ことが大切ですね。
海外へ目を向けてみると、医療系の国家資格を保有してオリンピックに出場している選手が数多くいます。医療資格があるとキャリアを中断しても復帰しやすいですし、キャリアを中断しても報酬の差が出にくいと感じています。医療資格があれば安心してチャレンジしやすいと思うので、ぜひ病院の外にGO OUT、飛び出してみてほしいです。
今や医療従事者は一般企業でも求められています。例えば、ドラム式洗濯機が普及してきたことで、可動域制限がある高齢者の方でも洗濯がしやすくなったように、これから高齢者が増えていく日本では、全分野でヘルスケアの知識が必要不可欠になるでしょう。
国家資格を保有していると社会的な信用もあるので、ますます他業界でも求められる場面が多く訪れると思います。病院の外へ一歩踏み出して、可能性をどんどん広げてほしいと強く思います。
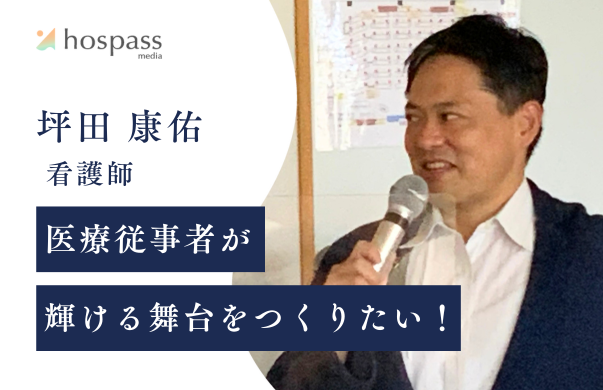
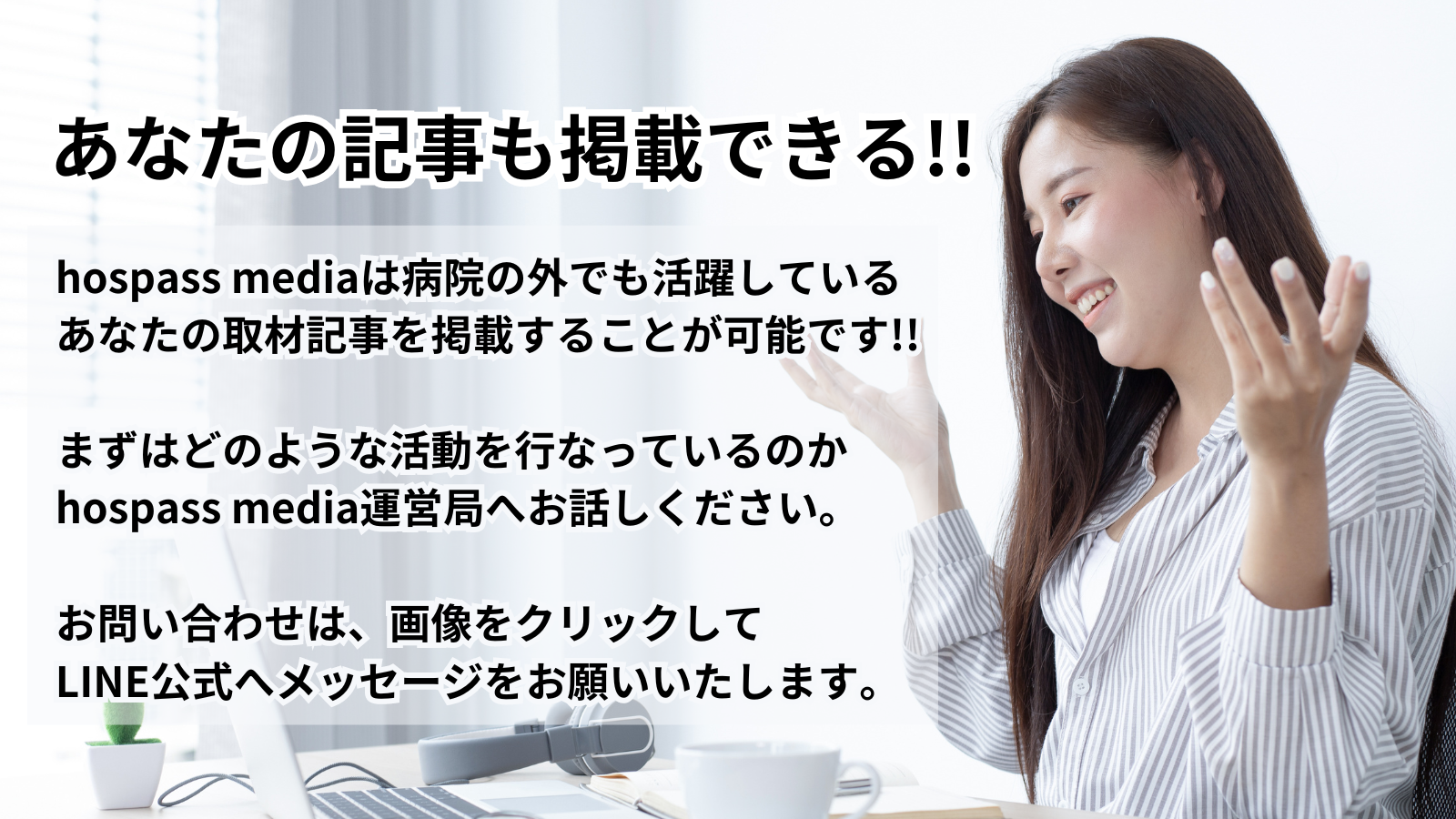

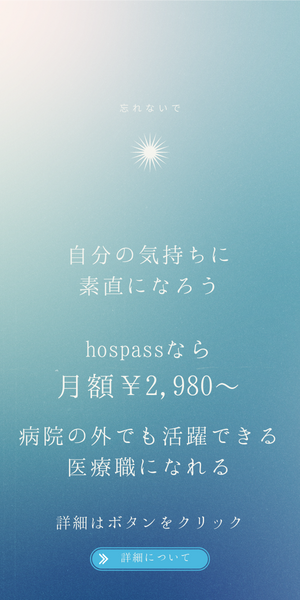

坪田康佑(看護師)
看護師免許を取得後、教員の道へ。医療とお金についての理解を深めるべく渡米しⅯBAを取得。リーマンショックをきっかけに、組織の成長をサポートするコーチング上場企業に従事した後、訪問看護事業や医療系AI事業の立ち上げを経験。現在は看護DX研修や訪問看護のM&Aなど、新しい医療に関する講演や執筆活動をしている。
看護師の視点で取り組んだ、ものづくり事業では、グッドデザイン賞を受賞。著書に『老老介護で知っておきたいことのすべて ―幸せな介護の入門書―』『看護管理者のためのコーチング実践ガイド ―臨床を動かすリーダーシップ―』があり、ブログ「DANs」でも情報を発信している。