- 小瀬古さんは資格を持たない状態で病院へ就職した!?
- 学生時代は精神科ではなく、身体の領域へ進むつもりだった
- オンライン研修プログラムの構想は約6年前から始まっていた!?
- 医療業界だけでなく、社会全体のメンタルヘルスリテラシーを高めたいという想いで活動されている
看護師の資格を取得するまでの経緯を教えてください

「精神科病院で働いていたこと親戚のひと言がきっかけでした」
当時の私はやりたいことが不明確で、とくにこだわりも無かったため進路に悩んでいました。そんな私に、精神科病院で働いていた親戚が「病院で働いてみないか」と声をかけてくれたんです。
正直、私には特別な使命感や強い意志はありませんでしたが、このひと言がきっかけで医療現場で働くことに興味を持ちましたね。また当時の精神科病院では、看護補助者のような資格を持たない方々が多く働いていました。そのような背景もあって、自分も病院で働いてみようという決意が固まったと思います。
実際に病院へ入職し、約1年間勤務しました。その後は、病院からキャリアアップの提案があったため、准看護師と正看護師の資格を取得して現在に至ります。

精神科でキャリアを積もうと思った理由を教えてください!
当時は男性看護師の活躍の場は限られており、オペ室で勤務する方が多かったです。しかし、私はオペ室で勤務するイメージは浮かばず、もともと興味のあった精神科に進む選択肢も浮かんできました。
なかなか結論を出せず、看護学校の先生や妻に相談しました。妻は「早めに精神科で経験を積んで、精神科領域を極める選択肢もありじゃない?」と背中を押してくれたんです。このひと言がきっかけで、精神科でキャリアを積もうという決心がつきましたね。
その後は、精神科認定看護師も取得しています。当時の私は経験年数が浅いため「もっとこんなケアがしたい」と思っていても、私の発言には影響力がありませんでした。
しかし、認定看護師を取得することで説得力が増し、尊敬している医師や上司とも対等な立場で意見交換ができると思ったんです。現状を打破したいという強い想いから、キャリアアップに至りました。
現在行っている事業について教えてください!

TOKINO Boardingというオンライン研修プログラムを提供しています。
現在、TOKINO Boardingという精神科訪問看護オンライン研修プログラムの事業を展開しています。当初は、法人向けの研修となる予定でした。しかし「これまで弊社のセミナーで学習してくださっていた方々の学びを止めたくない」という想いで、個人プランも整備しています。
具体的には、精神疾患別の知識や看護理論・GAFや看護計画の立て方など、精神科訪問看護の業務全般で役立つ知識をコンテンツにまとめました。また、ニーズの高まっている児童精神科領域を学べるコースや、マネジメント・ビジネスマナーを学べるビジネスコースも完備しています。
加えて、過去に開催してきた有料セミナーの多くが閲覧可能です。他にも「オントレ」という実践型の研修も整備しており、プログラム開始時点で100個以上のコンテンツが揃いました。私たちのオンライン研修プログラムは法定研修もカバーしているため、精神科訪問看護に必要な知識や技術を網羅的に学ぶことができます。
また、弊社の研修プログラムでは、各事業所の特性を踏まえたカスタマイズが可能です。そのため、教育体制の整備に関わるコストを抑えつつ、各事業所の特性を踏まえたスタッフ教育も実現できます。
現場に立っている皆さまには、ぜひ利用者様と接する訪問業務に注力していただきたいです。その時間をしっかりと確保するために、ぜひ弊社の研修プログラムがお役に立てると嬉しいなと思います。
現在の事業に至った背景を教えてください!

私たちが欲しかった研修プログラムを追い求めた結果です。
私たちが研修事業をスタートしたのは「自分たちが欲しかった学びの場を創ろう」という雑談がきっかけでした。他愛もない会話で「あの先生の話を別の角度で聞きたいよね」「こんな講義があったらいいのに」という意見が普段から出ていました。
しかし、その後もなかなか理想の研修は見つかりませんでしたね。「見つからないなら、自分たちで創ってしまおうか!」という結論に至り、約6年前から当事業の構想がスタートしています。
当時、現地開催のセミナーが決定し、100名を超える方々にご参加いただける予定でした。同時期に新型コロナウイルスが流行し、中止となってしまいましたが「いつかは必ず事業化させたい」という想いは消えなかったです。
事業を動かせない期間も続きましたが、いざ振り返ってみると、事業の方向性を見つめ直すいい機会だったと思います。特にZoomが普及したことで、オンライン開催という選択肢が増えたのは本当に大きなチャンスでした。
開発当初は「自分たちが学びたい内容」という要素が大きかったです。ただ、より多くの方々に届けられるようになったからこそ「せっかくやるなら、皆さんの役に立つような研修事業にしよう」と心境が変化していきました。
コロナ渦というピンチをチャンスに変えて事業の方向性を大きく軌道修正し、現在の形が出来上がっています。
日々の訪問業務や管理業務をしながら教育体制を整備するのは、とても負担が大きいのではないでしょうか。私たちも精神科訪問看護事業所を運営する中で、日々の訪問業務と教育体制の構築を並行して行うのは本当に苦労しました。
だからこそ、弊社のメンバーからも「教育システムの構築を外注できるサービスがあったら、絶対に使っていたよね」という声が満場一致で挙がりましたね。過去に現地やオンラインでセミナーを開催するなど、様々な試作を打ってきた経験が凝縮されて、弊社の研修プログラムが生まれています。
事業に詰まっている想い教えてください

社会全体のメンタルヘルスリテラシーを向上させたいです。
私たちの理念には「障害の有無に関わらず、すべての人が自分らしく生きられる世界をつくりたい」という想いが込められています。これは医療業界に限らず、一般企業も含めた社会全体に通ずる理念です。
この理念を実現するために、まずは精神科訪問看護の質を上げることが私たちの使命だと考えています。重度な精神疾患をお持ちの方はもちろん、診断の有無にかかわらずサイコーシスにある方々へのケアという大きな課題に挑んでいくつもりです。
このような課題をクリアしていくためには、私たちのみならず、精神科訪問看護の業界全体でケアの質を向上していかなければなりません。だからこそ、現在展開している「TOKINO Boardingオンライン研修プログラム」の普及とアップデートに注力していきたいと思います。
そして、私たちにはメンタルヘルスの事業に挑戦し続けてきたという強みがあります。その強みを活かして、最終的には精神科訪問看護の業界だけでなく、社会全体のメンタルヘルスリテラシーが向上するような事業にも挑戦していきたいです。
社会全体のメンタルヘルスのリテラシーが向上することで、すべての人が生きやすく、働きやすい社会が実現していくのではないかと考えています。
正直、まだくっきりとした形は見えていません。社会全体のメンタルヘルスリテラシーを向上させるために「私たちは一体どんな貢献ができるのか?」を常に模索し続けていきたいと思います。
事業を通してどんな社会を実現したいですか?

障がいがあってもなくても生きやすい社会を創造したいです。
私たちの事業は精神科訪問看護からスタートしており、精神科で診断を受けて治療を必要とされている方々のサポートを続けてきました。精神科が認知されていない時代もありましたが、現在はメンタルクリニックや精神科訪問看護が普及するなど、時代が変化しつつあります。
一方で、メンタルヘルスの問題は他人事と捉えている方が、まだまだ多いのではないでしょうか。しかし、メンタルヘルスの問題は医療従事者だけが担うものではなく、社会全体で取り組むべき課題なんです。
皆さんの周囲にも、打ち明けられないけれども「生きづらさ」を抱えている方々が数え切れないほどいるのではないでしょうか。「あの人は変わった人だ」「ただのコミュ障だろう」と捉えるのではなく、「その背景にはどんな要因があるのか」を考慮できる方が増えてほしいです。
また、違和感や生きづらさを抱える仲間に「何かあったの?」と一声かけられるような風潮が当たり前になっていけばいいなと思います。すべての人が心の健康を身近に感じ、他者の生きづらさを理解し支える世の中が実現できれば嬉しいです。
私の頭の中では、現在展開中の事業に加えて既にいくつかの手段が浮かんでいます。しかし、新型コロナウイルスで世間の情勢が一変したように、今後も社会は激しく変化していくはずです。そのような状況でも、私たちは「社会のために何ができるのか」を問い続けていきたいと思います。
そして「障がいの有無に関わらず、すべての人が自分らしく生きられる世界」の実現を目指して、メンタルヘルスリテラシー向上に向けた取り組みを続けていく所存です。
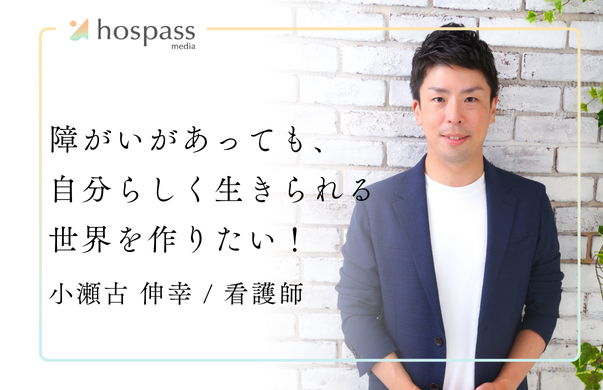
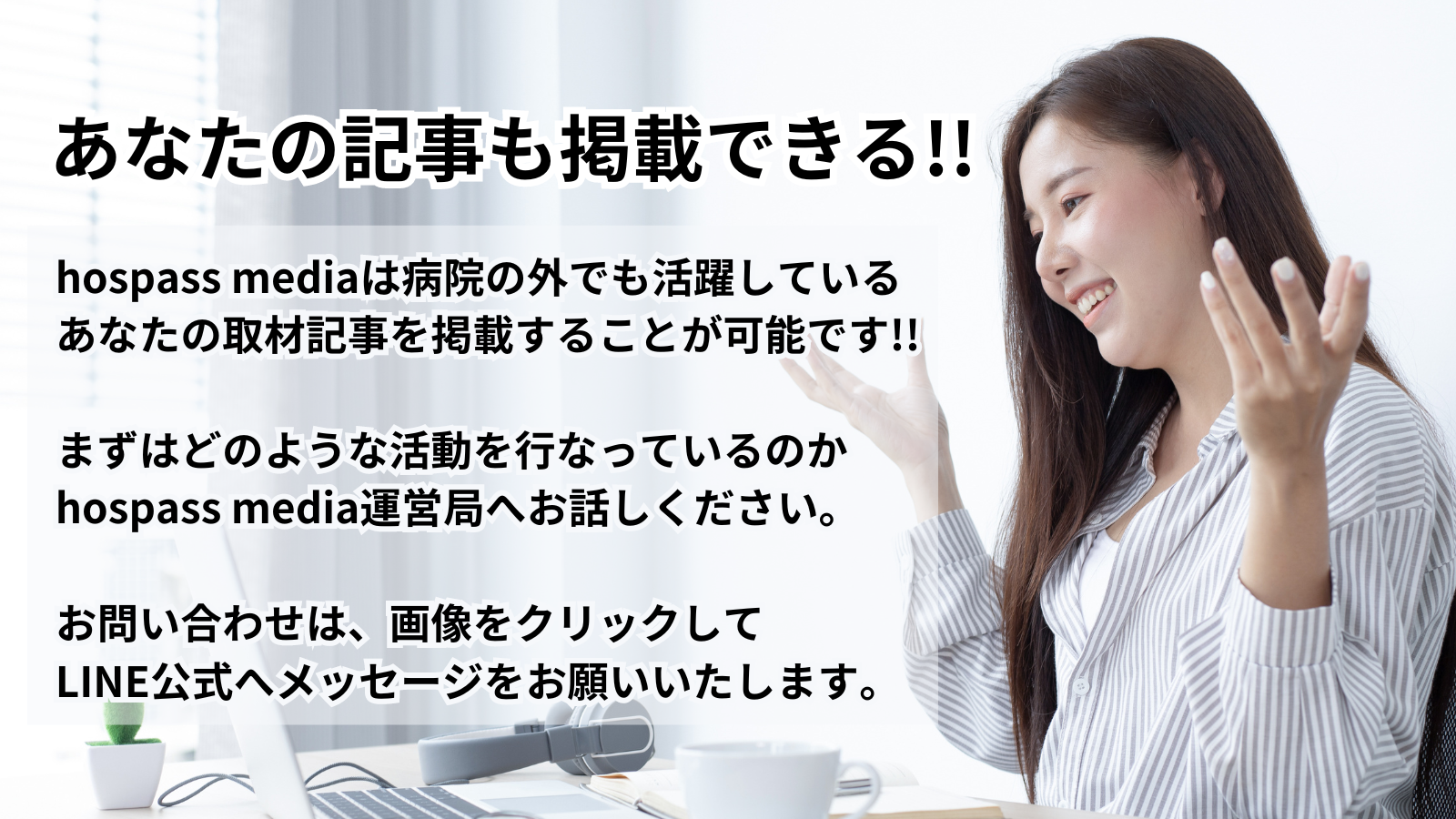

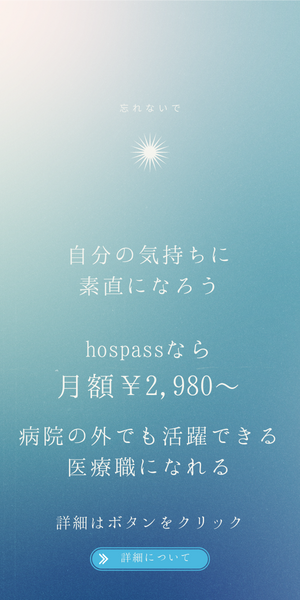

小瀬古 伸幸 (看護師)
親戚の言葉がきっかけで精神科病院へ就職。精神科領域の面白さに気がつき、無資格から精神科認定看護師までキャリアアップを経験した。現在は精神科訪問看護オンライン研修プログラムを開発・提供中。「障害の有無に関わらず、自分らしく生きられる方を増やしたい」という想いで活動されている。