以前【他人への親切行動が自分のモチベーションも上げる】とお話しさせて頂いたと思うのですが,
この現象は、親切をした事によりドーパミンが脳内に分泌され、「ランナーズハイ」ならぬ「ヘルパーズハイ」と呼ぶらしいです。
そんな親切心によるモチベーションを上げる方法を、スタンフォード大学が行なった研究がまた面白いことを言っていますので、早速みなさんに紹介します!
親切な行動は、受け手にメリットがあるわけではない。
いきなりですが研究者の名言を紹介します。
親切な行動は、受け手にメリットがあるだけではなく、行動する側にも「ヘルパーズハイ」という喜びの感情を作り出す。「人のために良いことをしよう」という教えは、個人の幸福を高める良い戦略になる。
残る問題は、ヘルパーズハイを作り出すベストな方法は何か?という点だ。
とのこと。
つまり何が言いたいかというと、親切により喜びが得られるのは確かなので、あとはどのタイミングで親切をするかが重要になってくる。
っということ。「親切のタイミングを図るとかちょっといやらしいですが。」、ってことでそんな話で研究を紹介!
目標の立て方によって効果に違いがでる
研究方法
543人の男女に2パターンの実験を行って
「適切な親切の方法」を調査しました。
- 抽象的な目標:「誰かを幸せにする」というゴールを設定
- 具体的な目標:「誰かを笑わせる」というゴールを設定
上記の内容で24時間以内に
親切な行動をしてもらいました
研究結果
- 具体的な目標のグループのほうが最終的な幸福感は高くなった。
研究の過程としては両グループとも取った行動に差がなく「プレゼントする」「面白い事を言う」「面白い動画を教える」など小さい親切を実践したようでした。
ではなぜ幸福度に違いが出たのか?研究チームはこう解釈しています。
- 具体的な目標の方が予測が現実的になるから
「誰かを幸せにする」だと幸せは人ぞれぞれの抽象的な目標なため向かうべきゴールが不明瞭なので尺度を測りづらいんですね。
「誰かを笑わせる」だと笑わせる事が明確なゴールになるので、やるべきことが具体的になり確かな出来事が残る。言われてみると確かにって感じですね。
さらに今回の研究では
「相手との関係や親切の種類は幸福度の差に影響しない」とも述べられており、親切の相手が友人ではなく、初対面の方でも親切で幸福度は上がり、また方法としても、何かをプレゼントすることや、冗談で笑わせただけでも全体の幸福度は上がったようです。
要するに、親切の効果は「期待と現実のギャップ」により幸福度に変化があるのではないか?と面白い仮説が立っております。
さらに、この結果をもとに
「会社も目標を具体的にした方が良いよね?」と提案しており、よくある理念に「お客さまを幸せに!」みたいなのじゃなくて、「お客さんの満足度を5%あげる」とか具体的なものにしよう!っと伝えてくれています。
当たり前のことですね。
具体的な事や数字を決めてしまえば、基準が設けられるので最終的に結果を比較でき幸せになれる。とのこと。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
個人でも会社でも集団でも「親切」で幸せになるためには、具体的な目標を決める必要がある。
何事にも大事ですよね、目標を決めるのは。ですが見落としやすい部分でもあるので、気をつけていきましょうね!
それではまたー!

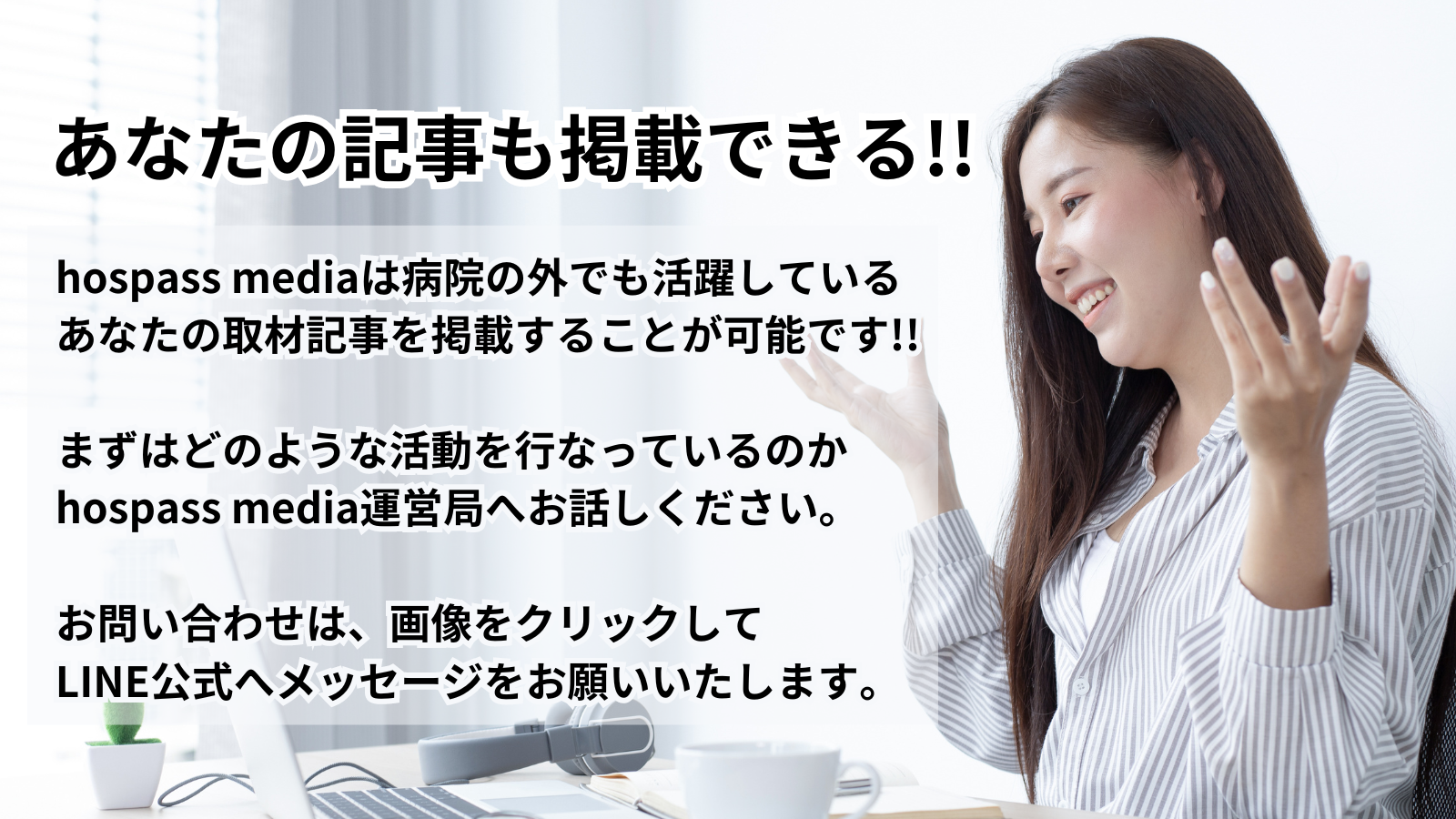

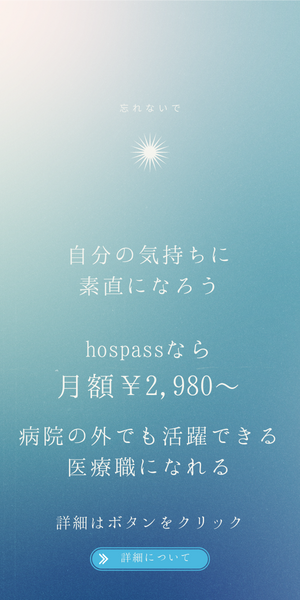

コメントを残す